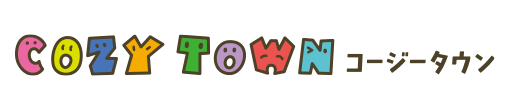「在宅看取り」と「人生会議」
奥山 光一

厚生労働省の人口動態調査によると、1980年は自宅で亡くなる人が全体のほぼ半数でしたが、2016年では病院で亡くなる人が7割を超えています(病院75.8%/自宅14.1%)。
超高齢社会が加速度的に進展し、医療的ケアが必要な高齢者の一層の増加が見込まれる中で、国は高齢者の長期入院の抑制と在宅医療へのシフトを進めており、今のように病院で最期を迎えることが難しくなる状況が近い将来訪れると思われます。滋賀県地域医療構想では、2013年に9,278人/日であった在宅医療等の医療需要は、2 025年には13,995人/日と約1.5倍に増加すると推計しています。また、2016年度に滋賀県が実施した「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査」によると、将来介護が必要になったときに介護を受けたい場所について「自宅で介護してほしい」が29.1%、人生の最終段階を迎えたい場所についても「自宅」が41. 9%と最も多くなっています。
こうした状況を踏まえて、県では、医療への依存度が高くなっても、自分の望む場所で生活したいという希望や、在宅で最期を迎えたいという選択肢の実現をめざして、在宅療養を支える体制づくりや、人生の最終段階の迎え方を県民のみなさんとともに考える機会を設けるなど「在宅看取り」の実践に向けた取り組みを進めています。
「在宅看取り」というと、人生の最期は「病院」か「自宅」かという話になりがちですが、その本質は「場所」ではなく、本人の希望する人生の最期の「迎え方」をいかに尊重していくかというところにあります。その人が人生の最期まで「よく生き抜く」ために、家族、専門職、ときにはご近所の方など、関係者が本人の思いに寄り添い、その意思決定を支えていく実践の過程が「在宅看取り」の取り組みではないかと思います。
厚生労働省では、人生の最終段階での医療・ケアについて本人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合う取り組み(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)に「人生会議」という愛称をつけて、その考え方を普及していこうとしています。
かつて、多世代家族が多く、地縁の結びつきが強かった時代には、人の死は日常生活のすぐそばにあり、人生の最期を迎える過程にゆかりの人がさまざまな形で自然に関わっていました。核家族化が進む今日、昔のような看取りが難しい中にあっても、専門職を含め、なじみの人たちの支えによって、本人が人生の最期の迎え方を自分で決められるよう環境を整えていく取り組みが「人生会議」であると思います。
人の「死」は点ではなく、「生(生活)」の延長上にあります。だからこそ、人が最期まで自分らしく生きていくためには、さまざまな人との関わりが必要になってきます。「在宅看取り」や「人生会議」は、そうした人々の「つながり」を紡ぐ実践でもあると思います。人はみな、いつでも、命に関わるような大きな病気やケガをして、命の危険が迫る状態になる可能性があります。私自身も「我が事」として、自分自身や家族の人生の最期の迎え方を一度考えてみようと思います。